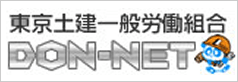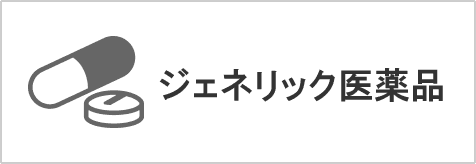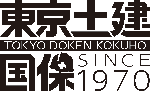保険料と保険料区分
東京土建国保組合が組合員から徴収する国民健康保険料は、公営国保と同じく「医療給付費分」、「後期高齢者支援金等分」および「介護納付金分」があります。
保険料はこれらすべてを合算して徴収しますが、保険料納入通知書は、保険料算定の透明化を図るため、内訳として、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分それぞれの金額を記載しています。
医療給付費分保険料(基礎賦課分)
病気やケガをしたときの医療費や健診などの保健事業の財源となる保険料
加入時に組合員から申告された就業実態区分(働き方)や年齢等に基づき、組合員と家族の保険料区分を決定します。
| 組合員 | 就業実態区分と年齢等に基づき、保険料区分(法人A種から法人C種と第1種から第7種の10区分)を決定します。 都外居住者は、東京都から補助金の交付を受けていないため、都内居住者より高い金額を設定しています。 |
| 家族 | 年齢と性別に基づき、保険料区分(成人男性、一般、高校生相当、中学生相当、小学生相当、幼児、乳児の7区分)を決定します。 ※成人男性、一般、高校生相当、中学生相当、小学生相当、幼児、乳児の順で4人目まで保険料を徴収します。5人目から保険料は徴収しません。 |
後期高齢者支援金分保険料(後期高齢者支援金等賦課額)
後期高齢者医療制度を支えるための財源となる保険料
| 組合員と成人男性家族 (23歳以上60歳未満の家族) |
組合員と成人男性区分の家族に賦課します。 ※成人男性が5人以上の場合は、5人目から保険料は徴収しません。 |
介護納付金分保険料(介護納付金賦課額)
介護保険制度を支えるための財源となる保険料
| 組合員・家族 共通 | 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)に賦課します。 ※1人につき一律の金額です。 ※第2号被保険者に該当する家族が5人以上の場合は、5人目から保険料は徴収しません。 |
●組合員の就業実態に基づく保険料区分
| 就業実態 | 保険料区分 |
| 法人事業所の代表者 | 法人A種 |
| 法人事業所の代表者のうち所得200万円超250万円以下の方 | 法人B種 |
| 法人事業所の代表者のうち所得200万円以下の方 | 法人C種 |
| 個人事業所の事業主 | 第1種 |
| 個人事業主のうち所得200万円以下の方 | 第2種 |
| 一人親方 | |
| 外注としての手間請け | 第3・4・5・6・7種 |
| 日当で働いているが、事業所は一定しない | |
| 特定の事業所で働いて、賃金をもらっている (法人事業所または従業員5人以上の個人事業所) |
|
| 特定の事業所で働いて、賃金をもらっているが 社会保険の適用対象外 |
保険料区分の定義と金額
| 保険料区分 | 定義 | 保険料 | 後期高齢者支援分(再掲) | |
| 都内居住者 | 都外居住者 | |||
| 組合員 | ||||
| 法人A種 | 法人事業所の代表者 | 39,550円 | 41,850円 | 10,700円 |
| 法人B種 | 法人事業所の代表者のうち、すべての所得(※)の合計額が200万円超250万円以下の方 | 35,850円 | 38,150円 | 9,700円 |
| 法人C種 | 法人事業所の代表者のうち、すべての所得(※)の合計額が200万円以下の方 | 31,650円 | 33,950円 | 8,500円 |
| 第1種 | 個人事業所の事業主 | 33,450円 | 35,750円 | 9,000円 |
| 第2種 | 一人親方及び法人事業所の代表者以外の役員及び第1種組合員のうち、すべての所得(※)の合計額が200万円以下の方 | 27,250円 | 29,550円 | 7,300円 |
| 第3種 | 常時又は日々事業所に雇用されている方 | 22,250円 | 24,550円 | 6,000円 |
| 第4種 | 第3種に該当する方で30歳以上35歳未満の方 | 22,250円 | 24,550円 | 6,000円 |
| 第5種 | 第3種に該当する方で25歳以上30歳未満の方 | 16,150円 | 18,450円 | 4,400円 |
| 第6種 | 第3種に該当する方で20歳以上25歳未満の方 | 12,150円 | 13,350円 | 3,300円 |
| 第7種 | 第3種に該当する方で20歳未満の方 | 9,350円 | 10,550円 | 2,500円 |
| ※1 | 組合員個人の所得で判定し、家族の所得は合算しません。 |
| ※2 | 適用期間は8月分保険料から翌年7月分保険料となります(法人B種、法人C種、第2種のみ)。 |
| ※3 | 毎月24日(土日祝日の場合は翌業務日)を締切日として、締切日までに国保組合で受付した届け出は当月からの変更となります。 |
| 保険料区分 | 定義 | 保険料 | 後期高齢者支援分(再掲) | |
| 都内・都外居住者 | ||||
| 家族 | ||||
| 成人男性 | 23歳以上60歳未満の男性 (学生、障害者、傷病加療により労務不能の人を除く) |
12,100円 | 3,300円 | |
| 一般 | 18歳以上の方で、成人男性以外の方 | 4,600円 | ― | |
| 高校生相当 | 15歳以上18歳未満の方 | 3,800円 | ― | |
| 中学生相当 | 12歳以上15歳未満の方 | 3,800円 | ― | |
| 小学生相当 | 7歳以上12歳未満の方 | 3,000円 | ― | |
| 幼児 | 3歳以上7歳未満の方 | 1,800円 | ― | |
| 乳児 | 3歳未満の方 | 1,800円 | ― | |
注意:40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者は、組合員・家族ともに1人4,200円が加算されます。
注意:年齢による保険料区分は、2025年4月1日の満年齢が適用されます。
成人男性(23歳以上60歳未満)で以下に該当する方は保険料が減額されます
| 状況 | 提出書類 | 届出と保険料変更の時期 | 適用期間 |
| 学生 ※学校教育法に規定する学校に在学する方(ただし、修学年限が1年未満の各種学校に在学する方は除く。) ※国民年金保険料の学生納付特例制度の対象となる方 |
◆家族保険料区分変更届 ◆在学証明書 (2025年4月1日以降の証明日で、証明日より3力月以内のもの) |
毎月24日(土日祝日の場合は翌業務日)までに国保組合で受付したものは受付月から変更になります。 ただし、6月24日までの受付分は4月までさかのぼって変更になります。 |
変更月から2026年3月まで ※翌年度も該当する場合は再度届け出が必要です。 |
| 障害者 | ◆家族保険料区分変更届 ◆次のいずれかひとつ
|
毎月24日(土日祝日の場合は翌業務日)までに国保組合で受付したものは受付月から変更になります。 | 一度届け出がされれば翌年度以降も保険料減額が継続適用されます ※翌年度以降の届け出は不要です。 |
| 病気やケガの治療等により労務不能の方 | ◆家族保険料区分変更届 ◆次のいずれかひとつ
|
毎月24日(土日祝日の場合は翌業務日)までに国保組合で受付したものは受付月から変更になります。 | 変更月から2026年3月まで ※翌年度も該当する場合は再度届け出が必要です。 |
産前産後・育児休業の保険料減免(免除)
産前産後期間の保険料が減免されます
被保険者が出産したとき、手続きなしで保険料が減免(還付)されます。早めに減免を受けたい場合は届出が必要です。
*妊娠12週を超えた出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)であること、2023年11月以降の出産が条件になります。
| 出産(予定)者 | 組合員 | 家族 |
| 減免期間 | 産前42日(多胎の場合は98日)の属する月から出産予定月の翌々月まで | 出産予定月の前月(多胎の場合は3カ月前)から出産予定月の翌々月まで |
| 減免される保険料 | 世帯全員分の保険料 | 出産者(家族)の保険料 |
※「出産予定月」とは、出産の予定日(出産日)が属する月のことです。
※減免期間が2024年1月~2024年3月の場合の届出期限は、2025年4月30日までです。届出期限までに国保組合へ届くようにしてください。
●出産育児一時金の直接支払制度等を利用している場合
被保険者が出産育児一時金の直接支払制度等を利用した際の情報をもとに国保組合が職権で減免決定します。減免決定後、国保組合から減免決定のお知らせを送ります。
●届出が必要な場合
| 出産(予定)者 | 組合員 | 家族 |
| 届出が必要な場合 |
|
|
| 提出書類 |
|
|
| 届出の時期 | 出産予定日の6カ月前から届出できます | |
組合員が育児休業を取得した期間の保険料が免除されます
保険料区分が第3種、第4種、第5種、第6種、第7種の組合員で、1歳未満の子を養育するために取得した14日以上の育児休業期間のうち、国保組合に加入してから1年経過後の期間は、申請により保険料が免除されます。
| 免除期間 免除される保険料 |
育児休業開始年月から終了日の翌日の属する月の前月まで(子が1歳の誕生日の前月まで)の世帯全員分の保険料 |
| 提出書類 |
|
| 分割取得 | 分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申請が必要) |
| 申請の時期 | 保険料免除の対象となる育児休業期間中 |
●就業実態区分により、育児休業期間の証明が異なります。
| 就業実態区分 | 休業証明 | |
| 1 | 健保適用除外承認を受けている従業員 | 育児休業等取得者申出書の写し(年金事務所の受付印が押されたもの) ※電子申請の場合は「厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(写し)」及び電子申請の到着番号が印字されたメールの写し |
| 2 | 健保適用対象外の従業員 【代表者・事業主が親族でない】 |
事業所の事業主・代表者の証明 |
| 3 | 親族が代表者・事業主の事業所の健保適用対象外の従業員(※) | 群長・分会長の証明 |
| 4 | 事業所の従業員以外(※) |
※健保適用対象外の組合員の場合、月ごとに群長・分会長の証明印のある「休業報告書」の提出が必要になります。
育児休業免除期間の延長(女性組合員のみ)
女性組合員で特別な事情がある場合は期間延長の申請をすることで、2歳まで延長することができます。
※①1歳~1歳6カ月、②1歳6カ月~2歳、それぞれ申請が必要です。
●必要な書類
- 育児休業保険料免除期間延長申請書
- 就業実態区分に応じた休業証明
- 特別な理由を確認できる書類 *下表参照
≪育児休業保険料免除期間延長申請の添付書類≫
| 特別な理由 | 確認書類 | |||
| 右記以外 | 健保適用除外を 受けている組合員 |
|||
| ① | 保育所に入所できない場合 | 不承諾通知書 | 「育児休業等取得者申出書(延長)」の写し ※年金事務所の受付印押印済のもの ※電子申請の場合は「厚生年金保険育児休業等取得者確認通知書(写し)」及ぴ電子申請の到着番号が印字されたメールの写し |
|
| ② | 子の養育を行っている組合員の配偶者が、やむを得ない事情 (ア~ウ)により養育が困難となったとき |
|||
| ア | 死亡したとき | 死亡が確認できる書類 (住民票、戸籍謄本等) |
||
| イ | 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により 育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき |
医師の診断書 | ||
| ウ | 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に 係る子と同居しないこととなったとき |
世帯分離を確認できる書類 (改製原住民票、除票等) |
||